(全日本ローソク工業会参照)
ローソクの起源

ローソクはその起源を調べてみると最初、蝋(蜜蝋)や脂肪に木の皮、ブドウのつるやその他木片などを束ねた松明(たいまつ)から発達したものと考えられており、古くはエジプト人やギリシャ人に知られ、蝋製の小神像やローマ人死面も有名であり、蜜蝋をパピルス草や藁の根を束ねたものに塗ったローソクを寺院で使用したとプリニウスの博物誌に記載されており、既にローソクは紀元前3世紀に存在しギリシャ末期に発見されたと考えられています。
東洋においても西京雑記には、漢の高祖の時代(BC3世紀末)関越(福建省)王が、蜜蝋二百枚を献品したと記されていたり、中国の戦国末期(BC3世紀頃)のものと認められる河南省洛陽権金村の墳墓から青銅製の燭台が発見されています。
東洋においても西京雑記には、漢の高祖の時代(BC3世紀末)関越(福建省)王が、蜜蝋二百枚を献品したと記されていたり、中国の戦国末期(BC3世紀頃)のものと認められる河南省洛陽権金村の墳墓から青銅製の燭台が発見されています。
日本におけるローソクの歴史
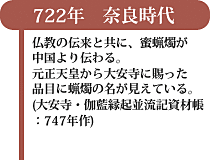
日本でローソクが最初に登場したのは奈良時代。
当時のローソクは中国から輸入された蜜蝋ローソクと考えられています。
恐らく、仏教の伝来とともにあわせて伝わったのでしょう。
当時のローソクは中国から輸入された蜜蝋ローソクと考えられています。
恐らく、仏教の伝来とともにあわせて伝わったのでしょう。
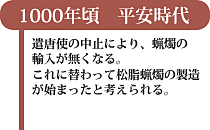
平安時代になり、蜜蝋に代わって松脂ローソクの製造が始まったと考えられています。
その後、和ローソクと呼ばれるはぜの蝋やうるしの蝋などを使ったものに代わり、江戸時代にはローソクと松ヤニと混ぜてハードワックスにしていました。
その後、和ローソクと呼ばれるはぜの蝋やうるしの蝋などを使ったものに代わり、江戸時代にはローソクと松ヤニと混ぜてハードワックスにしていました。
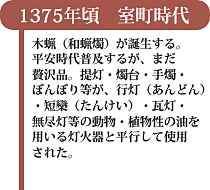
また江戸時代には木蝋の原料となるハゼノキが琉球から
伝わり、外出用の提灯のための需要が増えたこともあって、和ローソクの生産量が増えました。
和ローソクは裸で使うより提灯に入れて使うことが多かったので、蝋が減っても炎の高さが変わりにくいように
上の方が太く作られていました。
伝わり、外出用の提灯のための需要が増えたこともあって、和ローソクの生産量が増えました。
和ローソクは裸で使うより提灯に入れて使うことが多かったので、蝋が減っても炎の高さが変わりにくいように
上の方が太く作られていました。
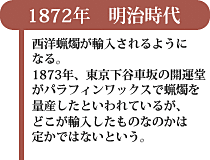
1818年ブラコノー、シナモンによって初めてステアリンローソクを製造し、1830年ごろにはパラフィンローソクが作られました。
しかし、地方の農村漁村までローソクが行き渡ったのは、明治時代になって西洋ローソクの製造が行われてからでした。
しかし、地方の農村漁村までローソクが行き渡ったのは、明治時代になって西洋ローソクの製造が行われてからでした。

在来の和ローソクは、手工業的に製造され色も黄褐色で光度もまことに暗いものでしたが、西洋ローソクは、機械的に多量に製造され、その色も乳白色で美しく、光度も明るいためにその伝来、普及に伴って在来の和ローソクは、急激に衰退してしまいました。
